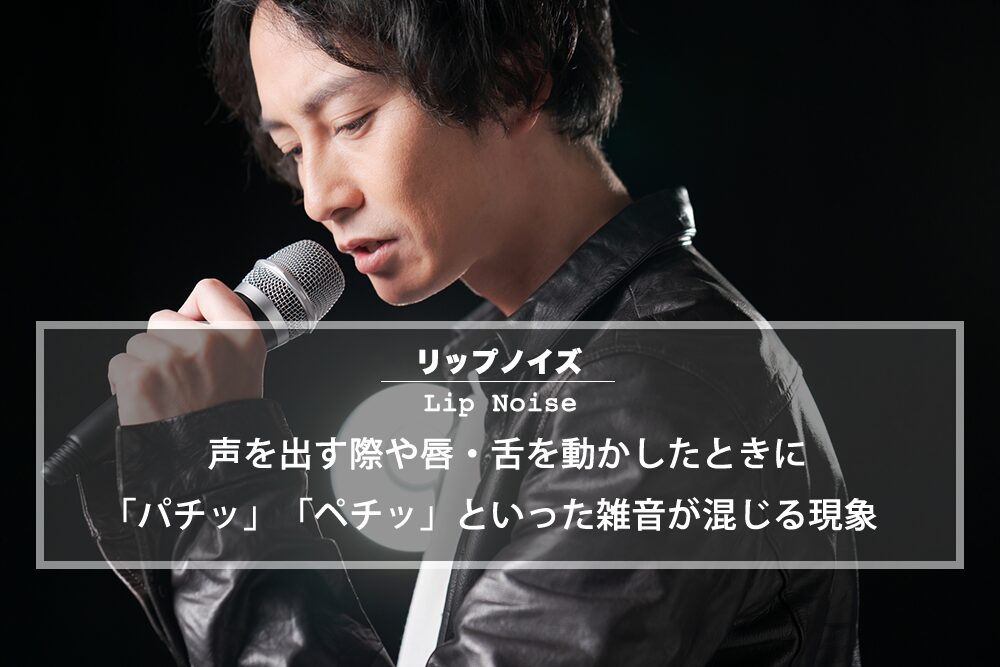リップノイズとは、声を出す際や唇・舌を動かしたときに「パチッ」「ペチッ」といった雑音が混じる現象のことです。自分では気づきにくいのに、聞き手にとっては耳障りに感じられるため、多くの人が悩まされています。
特にカラオケやレコーディング、配信、電話会議、スピーチといったマイクを使う場面では目立ちやすく、不快な印象を与える原因になりがちです。歌や話の内容が良くても、雑音が混ざるだけで説得力や聴き心地が損なわれることもあります。
本記事では、リップノイズの仕組みやポップノイズとの違いを明らかにした上で、具体的な原因と効果的な対処法を徹底解説します。
目次
リップノイズは唇や舌を動かした時に起こる雑音
リップノイズは、唇や舌の動きによって生じる摩擦音や唾液の粘度に由来する雑音です。
特に、声と声の間にできる「無音部分」や、言葉の語尾で目立つ傾向があります。普段の会話では気にならない場合でも、マイクを通すと音が強調されるため、聞き手にとっては不快に感じられやすくなります。
リップノイズの基本的な仕組み
唇を閉じた状態から急に開いたり、舌が口内で動いたりするときに、粘り気を帯びた唾液が引き剝がされることで「ペチッ」や「パッ」といった短い音が発生します。これは物理的な現象であり、唾液の量や質によって大きさや頻度が変わります。
また、発声に伴う息の流れも影響し、強い息が唇の表面を震わせて雑音を増幅させることがあります。
プロの現場でも問題視される理由
録音スタジオや配信環境では、わずかなリップノイズもマイクが拾ってしまうため、解決すべき課題となっています。
不要な雑音が混ざると編集でカットする必要があり、時間やコストが増える要因になります。さらに、ナレーションや歌声に雑音が残ると、全体の印象が損なわれるため、プロの現場では細心の注意が払われています。
そのため、リップノイズを抑えることは、趣味で歌う人からプロの声優やシンガーに至るまで共通の課題といえるのです。
リップノイズとポップノイズは種類の異なる雑音
リップノイズとよく混同されるのが「ポップノイズ」です。
どちらもマイク録音で目立つため同じ雑音のように感じられますが、発生原因や対策はまったく異なります。まずは両者の特徴を押さえ、混同しないように理解しておきましょう。
リップノイズの特徴
リップノイズは、唇や舌、唾液に由来する短い「パチッ」「ペチッ」という高めの音が特徴です。発声の合間や語尾で出やすく、特に口の乾燥や緊張による唾液の粘りが強いと頻発します。
ポップノイズの特徴
一方、ポップノイズは発声そのものではなく、息がマイクに直接当たることで「ボフッ」という低音が混じる現象です。特に「パ」「バ」「フ」といった破裂音の発音時に強く出やすく、発声法やマイクとの距離が主な要因となります。
発声以外では、オーディオアンプやギターアンプ、エフェクターなどの電源オンオフ時にスピーカーから「ボンッ」という音が鳴る現象を指す場合もあります。こちらは直流電圧が原因で、発声のポップノイズとは異なるものです。
2つのノイズの違いを整理
| リップノイズ | ポップノイズ | |
|---|---|---|
| 主な原因 | 唇や舌の摩擦
唾液の粘度 |
息がマイクに当たる |
| 発生場所 | 口内 | マイク |
| 音の特徴 | パチッ、ぺチッといった短い音 | ボフッという低音 |
| 主な対策 | 水分補給、発声の改善、環境調整 | マイク位置調整、ポップガードの使用 |
上記のように、リップノイズは「口内の動き」、ポップノイズは「息の当たり方」という根本的な違いがあります。それぞれに合わせた正しい対策を取ることが、快適な音声を実現する第一歩です。
リップノイズは聞き手を不快に感じさせる可能性がある
リップノイズは、本人にとっては意識しにくいものですが、聞き手にとっては強い不快感を与える要因になります。特にマイクを通した音声では雑音が強調され、相手の集中を妨げることがあります。
ここでは、シーン別にリップノイズが与える影響を見ていきましょう。
スピーチや授業では集中を妨げてしまう
スピーチや授業の場では、リップノイズが混ざることで内容よりも雑音が気になってしまいます。聴衆は話の内容に集中できず、説得力や理解度が下がる結果につながります。特に教育現場や講演では、聴き手の学習効果や納得感に悪影響を及ぼすリスクがあります。
エンタメや配信では「聴き心地の悪さ」につながる
歌や配信の場面では、リップノイズは聴き手に「心地よさの欠如」を感じさせます。
音楽やトークの内容が魅力的でも、ノイズが頻発するとリスナーが離れてしまい、再生数や視聴時間の低下を招く恐れがあります。クリエイターにとっては大きな機会損失となるため、無視できない課題です。
ビジネスシーンへの悪影響
オンライン会議や商談では、リップノイズが相手に「不快」「聞き取りづらい」といった印象を与えます。音声が不明瞭になることでコミュニケーション効率が下がり、ビジネス上の信頼関係にも影響を及ぼす可能性があります。
特に第一印象が重要な商談や面接の場では注意が必要です。
不快なリップノイズが鳴ってしまう7個の原因
リップノイズの原因は一つではなく、人によって異なる複数の要因が関わっています。そのため、改善を目指すには自分に当てはまる原因を見極めることが重要です。
ここでは代表的な7つの原因を解説し、どのような場面で起こりやすいかを整理していきます。
原因①:唇や舌の乾燥
唇や舌が乾燥していると、動かしたときに摩擦音が生じやすくなります。
唾液の分泌が不足することや、口呼吸、エアコンによる乾燥環境が主な原因です。特に冬場や長時間の発声では乾燥が強まり、リップノイズが発生しやすくなります。
原因②:唾液の粘度が高い
緊張時や糖分の多い飲食をした後は、唾液が粘りやすくなります。
脱水状態でも唾液が濃縮されるため、口内で音が鳴りやすくなります。「ネバネバした唾液」は、リップノイズを増やす大きな要因です。
原因③:マイクとの距離・角度が不適切
マイクが口に近すぎたり、正面から息や口音を直接拾う位置にあったりすると、リップノイズが強調されます。特に録音や配信では、数センチの距離の違いで音質が大きく変化します。
原因④:発声方法の問題
喉に余計な力が入ると、口の開閉がスムーズでなくなり、摩擦音が生じやすくなります。また、滑舌が悪いと舌や唇の動きが不自然になり、リップノイズを引き起こします。
原因⑤:姿勢や呼吸の乱れ
浅い胸式呼吸や猫背の姿勢では、息の流れが不安定になります。呼吸が乱れることで唇や舌の動きに影響が出て、リップノイズが生まれやすくなります。
原因⑥:姿勢や呼吸の乱れ
湿度が低い部屋や、エアコンの風が直接当たる環境では口内が乾燥しやすくなります。適切な湿度管理(40〜60%程度)ができていない環境では、リップノイズの発生頻度が高まります。
原因⑦:健康状態や習慣
水分不足、口腔ケアの不足、喫煙習慣などは口内環境を悪化させ、リップノイズを助長します。体調が優れないときや生活習慣が乱れているときも、雑音が目立ちやすくなります。
チェックリスト:リップノイズの主な原因
| 原因 | チェックポイント |
|---|---|
| 唇や舌の乾燥 | 長時間話すと口が乾く、エアコン環境にいる |
| 唾液の粘度が高い | 緊張すると唾液がネバつく、糖分を多く摂る |
| マイクとの距離・角度 | マイクを口の真正面に近づけすぎている |
| 発声方法 | 喉に力が入る、滑舌に自信がない |
| 姿勢や呼吸 | 猫背、浅い呼吸になっている |
| 録音環境 | 室内が乾燥している、加湿器を使っていない |
| 健康状態や習慣 | 水分摂取が少ない、喫煙や口腔ケア不足がある |
このチェックリストを活用することで、自分のリップノイズの原因を見極めやすくなります。複数の要因が重なっているケースも多いため、幅広く改善ポイントを確認することが大切です。
リップノイズが起きないように発声する対処法
リップノイズは一見小さな雑音ですが、聞き手にとっては意外と大きなストレスになります。中には一度の工夫で改善できるケースもあれば、日常的な習慣の見直しが必要なケースもあります。
ここでは、今日から実践できる対策と、長期的に取り組むべき改善法を見ていきましょう。
対処法①:水分補給と口腔ケア
口内が乾燥すると、唇や舌がスムーズに動かずリップノイズが生じやすくなります。
こまめな水分補給は最も基本的な対策です。常温の水を少量ずつ飲むことで粘度の高い唾液を防ぎ、音声を安定させます。また、うがいで口内を潤し、リップクリームや舌の保湿ケアを取り入れることも効果的です。
特に長時間の収録や配信前には意識的に準備するとよいでしょう。
以下の記事でカラオケや歌う前の飲み物のおすすめと避けたほうがいいものを紹介しています。

対処法②:正しい発声法を身につける
リップノイズを抑えるためには、単に口元を潤すだけでは不十分です。声の出し方そのものを整えることで、根本的にノイズの発生を減らすことができます。
以下では、基本となる呼吸法や滑舌トレーニングについて解説します。
トレーニング①:声帯に頼りすぎない呼吸法
喉に過度な力を入れると、口の開閉が不自然になりリップノイズを誘発します。そこで重要なのが腹式呼吸です。横隔膜を使って空気を取り込み、余裕のある発声を行うことで口腔内の動きが滑らかになり、ノイズの軽減につながります。
トレーニング②:滑舌トレーニング
舌や唇の動きが硬いと、発声の際に余計な摩擦音が生じます。
リップロール(唇を震わせる練習)や、母音を使った発声練習は筋肉を柔軟にし、自然でクリアな発音を助けます。こうしたトレーニングを毎日のルーティンに組み込むと、ノイズ対策だけでなく声全体の明瞭さも向上します。
対処法③:マイクテクニックの工夫
どれだけ発声を改善しても、マイクとの距離や角度が不適切であればノイズを拾いやすくなります。
理想は口元から指2〜3本分程度離すことで、真正面ではなくやや斜めに位置取ると余計な雑音を抑えられます。また、ポップガードを使用すれば、破裂音や息の吹きかけによるリップノイズを効果的に防げます。
対処法④:録音・配信環境の改善
音声環境そのものも大きな影響を与えます。
湿度が低すぎると口腔内の乾燥が進み、ノイズが目立ちやすくなります。加湿器を用いて湿度40~60%を保つことが推奨されます。エアコンの風が直接口や顔に当たる状況も避け、できるだけ安定した環境を整えることが望ましいです。
対処法⑤:専門的な改善法
自分で工夫しても改善が難しい場合は、専門家のサポートを受けるのも有効です。
ボイストレーナーによる発声指導では、呼吸や口の動きを客観的にチェックしてもらえます。また、歯科医や口腔ケア専門家に相談すれば、口内環境そのものを整えられ、ノイズの根本改善につながります。
おわりに
リップノイズはプロのナレーターや声優でも悩むことがあるほど、誰にでも起こり得る現象です。しかし、原因を理解し、適切な対策を講じれば確実に改善が可能です。
日常的な水分補給や滑舌トレーニングのように「今日からできるケア」と、腹式呼吸や専門的なトレーニングといった「長期的な改善策」を組み合わせることで、より安定した発声環境を築けます。
聞き手に快適な音声を届けるためにも、プロと同じように意識的にリップノイズ対策を実践していくことが大切です。