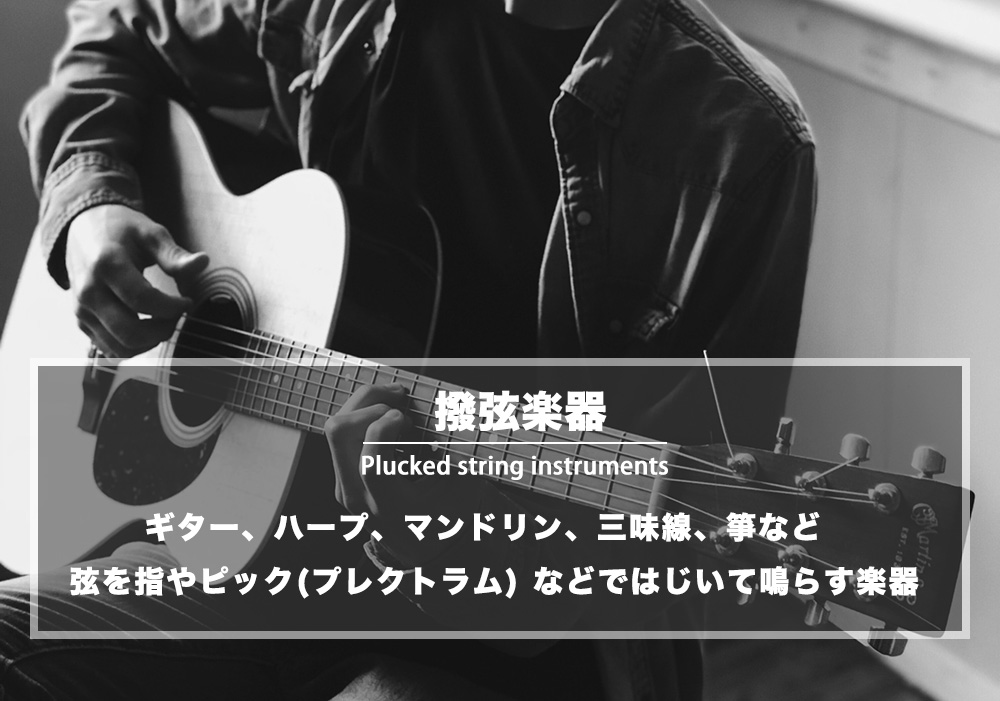撥弦楽器(はつげんがっき)とは
- 【読み方】はつげんがっき
- 撥弦楽器は、弦鳴楽器(弦を振動させて音を発する楽器【注1】)のうち、弦を指やピック(プレクトラム)などではじいて音を鳴らす楽器の総称。
※プレクトラム:弦をはじいて音を鳴らすための道具。ピックとも呼ぶ。 - 撥弦楽器の例:
ギター、リュート、マンドリン、ハープ、チェンバロ、ツィター(チター)、三味線、箏(そう)など。
└ 鍵盤楽器であるチェンバロはプレクトラムで弦を弾いて発音するため撥弦楽器に分類されるが、同じ弦鳴楽器であってもピアノは弦を叩いて発音するため打弦楽器に分類される。
└ ヴァイオリンには弦を指ではじいて音を鳴らすピチカートという奏法があるが、基本的に弓で弾く楽器であるため擦弦楽器(さつげんがっき)に分類される。 - 「撥」の字には2つの読み方がある。
【はつ】「はじく」の意
【ばち】「弦をはじいて鳴らす道具」の意 - 英語では「Plucked string instruments」という。
※「pluck(plˈʌk)」は、「引っ張る」や「摘み取る」といった意味を持つ単語で、音楽においては「(弦を指などで)爪弾く」「かき鳴らす」という意味で使われる
【注1】
弦鳴楽器(げんめいがっき):
弦鳴楽器は、楽器分類法の「ザックス=ホルンボステル分類【注2】」に基づいた楽器分類のひとつ。ザックス=ホルンボステル分類では、楽器を「体鳴楽器」「膜鳴楽器」「弦鳴楽器」「気鳴楽器」「電鳴楽器」の5つに分類する。
【注2】
ザックス=ホルンボステル分類:
ドイツ出身の音楽学者であるクルト・ザックスと、オーストリア出身の比較音楽学者であるエーリヒ・モーリツ・フォン・ホルンボステルによる共著論文『楽器の分類法』で提唱された楽器分類法。
ヴァイオリン、チェロ、コントラバスなど、弦を弓や棒でこすって鳴らす楽器は「擦弦楽器」と呼ぶ。詳しくは以下の記事で解説。
あわせて読みたい
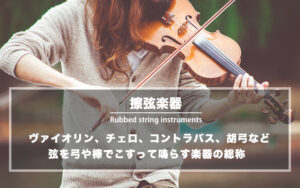
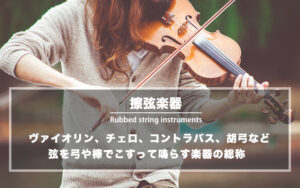
擦弦楽器とは:ヴァイオリンやチェロなど弦を弓や棒でこすって音を鳴らす楽器の総称
擦弦楽器(さつげんがっき)とは 【読み方】さつげんがっき 擦弦楽器は、弦鳴楽器(弦を振動させて音を発する楽器【注1】)のうち、弦を弓や棒などでこすって音を鳴らす...
ピアノや揚琴など弦を打って鳴らす楽器は「打弦楽器」と呼ぶ。詳しくは以下の記事で解説。
あわせて読みたい


打弦楽器とは:ピアノや揚琴など弦を打って音を鳴らす楽器の総称
打弦楽器(だげんがっき)とは 【読み方】だげんがっき 打弦楽器は、弦鳴楽器(弦を振動させて音を発する楽器【注1】)のうち、弦を打って音を鳴らす楽器の総称の総称。...