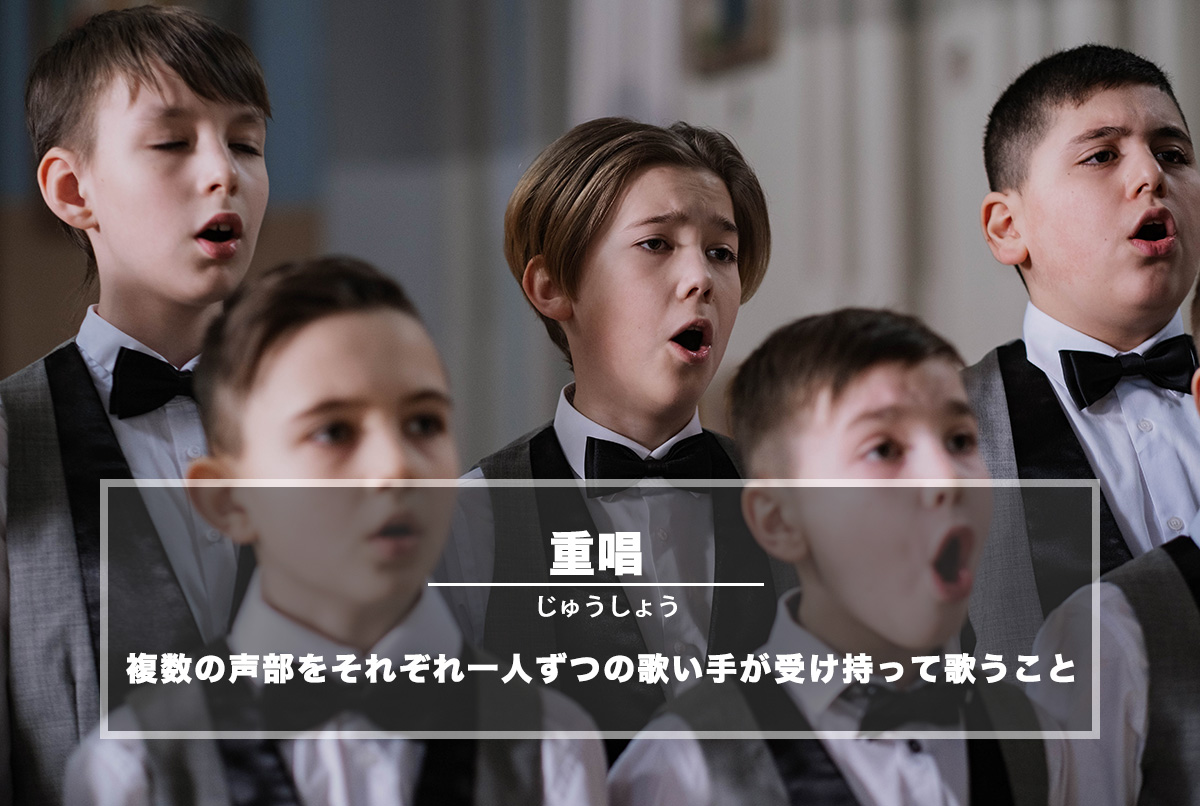重唱とは:複数の声部をそれぞれ一人ずつの歌い手が受け持って歌うこと
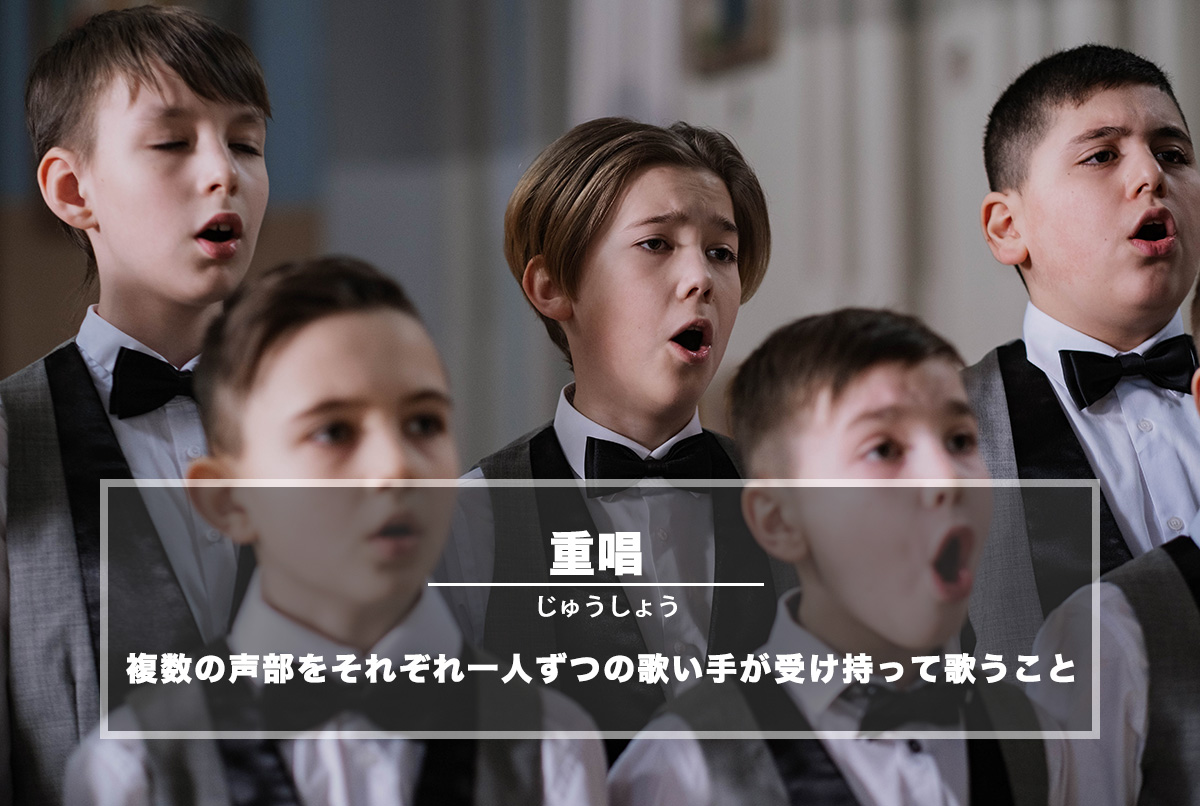
重唱(じゅうしょう)とは
- 【読み方】じゅうしょう
- 重唱は、声楽において複数に分かれた声部をそれぞれ一人ずつの歌い手が受け持って歌うこと。
→声部(パート)の解説
- 多声部の歌唱形態のひとつで、重唱では各声部を受け持つのは一人ずつ。
- 伴奏を伴う歌唱、伴奏を伴う歌唱(ア・カペラ)のいずれでも各声部の担当者が一人ずつであれば重唱と呼ぶ。
- 連唱(れんしょう)ともいう。連唱=重唱
- 二重唱(デュエット)、三重唱(トリオ)、四重唱(カルテット)、五重唱(クインテット)など、歌い手の人数に応じて重唱の前に数字が加わる。
五重唱であれば5人の歌い手による重唱という意味である。
- 対義語は独唱(どくしょう)。
- 複数の楽器で構成されるアンサンブルで、各声部をそれぞれ一人ずつの演奏者が担当して演奏する場合は「重奏(じゅうそう)」という。
重唱、合唱、斉唱の違い
- 重唱(じゅうそう)
複数に分かれた声部(パート)を各一人の歌い手が受け持って歌うこと。
- 合唱(がっしょう)
複数に分かれた声部(パート)をそれぞれ複数の歌い手が受け持ち、一つの響きをなすように歌い合わすこと。
複数の声部で構成され、それぞれの声部を複数の歌い手が歌う。
※伴奏なしの合唱はア・カペラと呼ぶ。
→合唱の解説
- 斉唱(せいしょう)
複数人が同じメロディーを歌うこと。
→斉唱の解説