擦弦楽器(さつげんがっき)とは
- 【読み方】さつげんがっき
- 擦弦楽器は、弦鳴楽器(弦を振動させて音を発する楽器【注1】)のうち、弦を弓や棒などでこすって音を鳴らす楽器の総称。
- 擦弦楽器の例:
ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロなどのヴァイオリン属、コントラバス、ラバーブ、胡弓(こきゅう)、馬頭琴(ばとうきん)、牙箏(アジェン)、ハーディ・ガーディなど。 - 「擦」の読みと意味
【読み】さつ
【意味】こする、さする、すれる(擦れる) - 英語では「Rubbed string instruments」という。
※「rubbed」は「rub(rʌbd)」の過去形/過去分詞形
「rub」は、「こする」「擦れる」「掻く」という意味を持つ単語 - 打弦楽器や撥弦楽器と違って持続音を出すことができ、管楽器のように呼吸に左右されずに音を長く伸ばすことができる。
- 弓などでこすって演奏することを、「擦奏(さっそう)」や「弓奏(きゅうそう)」と呼んだりする。
【注1】
弦鳴楽器(げんめいがっき):
弦鳴楽器は、楽器分類法の「ザックス=ホルンボステル分類【注2】」に基づいた楽器分類のひとつ。ザックス=ホルンボステル分類では、楽器を「体鳴楽器」「膜鳴楽器」「弦鳴楽器」「気鳴楽器」「電鳴楽器」の5つに分類する。
【注2】
ザックス=ホルンボステル分類:
ドイツ出身の音楽学者であるクルト・ザックスと、オーストリア出身の比較音楽学者であるエーリヒ・モーリツ・フォン・ホルンボステルによる共著論文『楽器の分類法』で提唱された楽器分類法。
ギターやハープなど弦をはじいて鳴らす楽器は「撥弦楽器」と呼ぶ。詳しくは以下の記事で解説。
あわせて読みたい
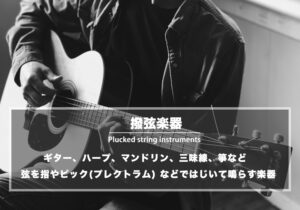
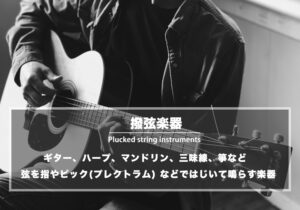
撥弦楽器とは:ギターやハープなど弦をはじいて音を鳴らす楽器の総称
撥弦楽器(はつげんがっき)とは 【読み方】はつげんがっき 撥弦楽器は、弦鳴楽器(弦を振動させて音を発する楽器【注1】)のうち、弦を指やピック(プレクトラム)など...
ピアノや揚琴など弦を打って鳴らす楽器は「打弦楽器」と呼ぶ。詳しくは以下の記事で解説。
あわせて読みたい


打弦楽器とは:ピアノや揚琴など弦を打って音を鳴らす楽器の総称
打弦楽器(だげんがっき)とは 【読み方】だげんがっき 打弦楽器は、弦鳴楽器(弦を振動させて音を発する楽器【注1】)のうち、弦を打って音を鳴らす楽器の総称の総称。...

