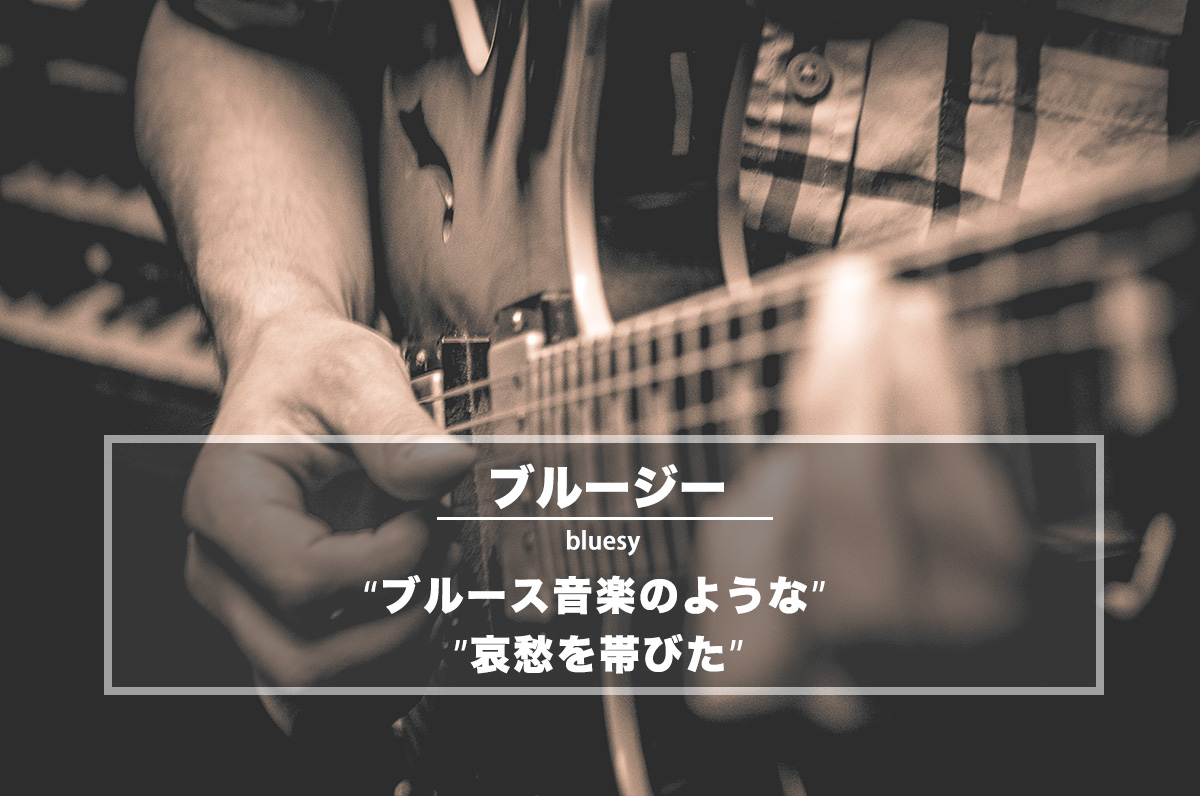ブルージー (bluesy) とは:「ブルース音楽のような」や「哀愁を帯びた」という意味
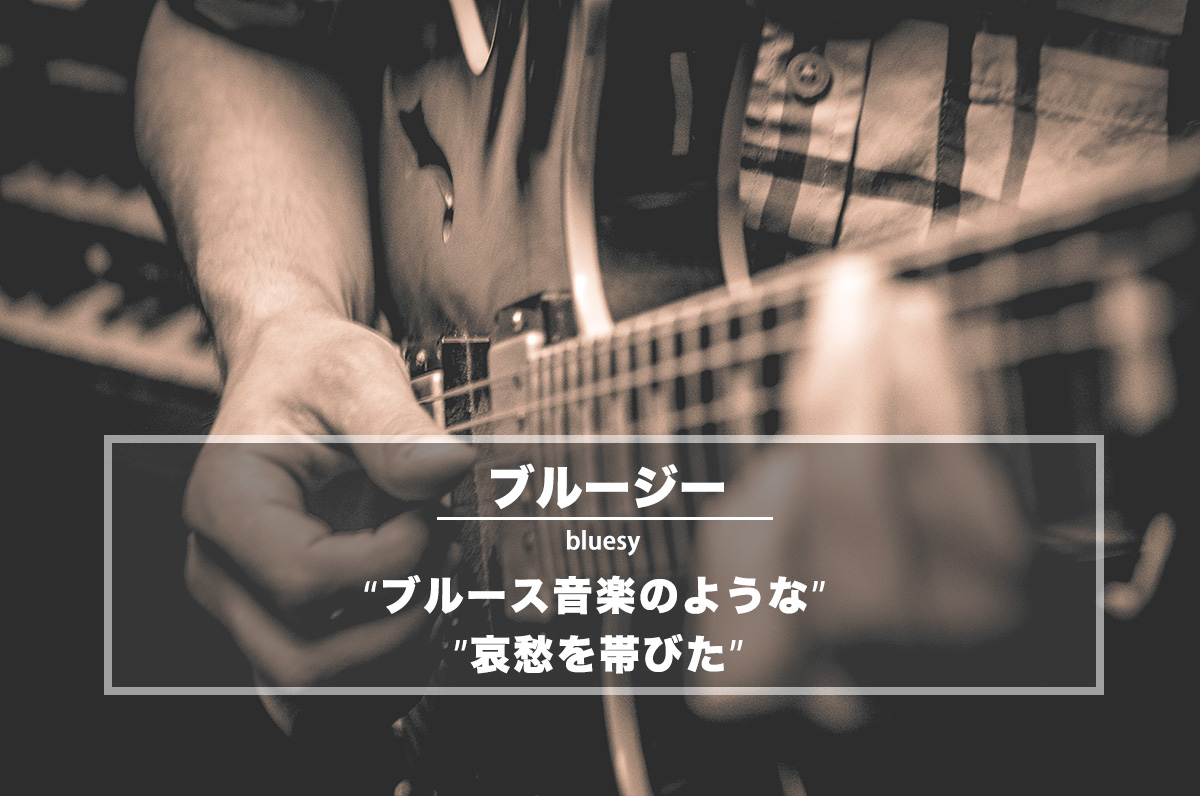
ブルージーとは
- ブルージー(bluesy)とは、「ブルース音楽のような」や「哀愁を帯びた」という意味の言葉。
- もともと「ブルースのような」という意味の単語だが、ブルース音楽の持つ哀愁や物悲しさを指して「哀愁(や憂い)を帯びた」という意味で使われたり、「渋い」という意味でも使われたりする。
- 日本語ではBluesをブルースと発音したり表記したりするが、
英語での本来の発音は「blúːz(ブルーズ)」である。
- ブルース音楽の持つ哀愁のあるムードやゆっくりとした強いリズムを感じさせる歌唱や演奏に対して、「ブルージー」と表現したりする。
- 哀愁を帯びた声質や歌い方をブルージーな歌声と表現したり、ブルースのような物悲しさを感じさせるギターに対する表現に使う。
ブルースとは
- ブルースは、19世紀半ばにアメリカの黒人たちによって生み出された音楽。
- ブルースは、「3行形式の歌詞」「1コーラス=12小節」を基本スタイルとする。
- セブンス・コードを使った伴奏、およびブルーノート・スケールを使った物悲しさや哀愁を帯びたメロディが特徴。
※ブルーノート・スケール:メジャー・スケールに第3音、第5音、第7音を半音下げた音(♭3、♭5、♭7)を加えた8音から成るスケール
bluesyの解説
- 「bluesy」は、名詞の「blues」に接頭辞の「-y」が付いた形容詞。
※「blues」は「憂鬱」を意味する単語。
- 接頭辞「-y」は単語を形容詞化または名詞化する役割を持つ。
- 「-y」によって名詞を形容詞化した場合、単語に以下の意味が加わる。
①「〜でいっぱいの(〜で満ちた)」「〜の性質をもつ」
②「〜に似た」「〜を思わせる」
- 「bluesy」を①と②それぞれに当てはめると以下のように解釈できる
①で解釈→「ブルースの性質を持つ」
②で解釈→「ブルースを思わせる」